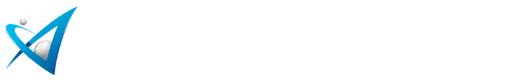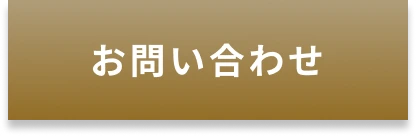1. プロダクト開発におけるセキュリティの重要性
セキュリティを無視できない理由
今や、プロダクト開発にセキュリティ対策を組み込むのは当たり前になっています。
技術が進化する一方で、サイバー攻撃もどんどん進化・激化していて、セキュリティ対策を何もしないままでは攻撃者のターゲットになります。
特にリリース後にセキュリティの問題が見つかると、信頼が一気に崩れてしまう可能性もあります。
セキュリティ対策を後回しにすることは、最終的に大きなリスクを抱え込むことにつながります。
開発前の段階からセキュリティ対策の方法についてしっかりと考えていきましょう。
サイバー攻撃を受けたときの損害
日本国内でも、セキュリティの不備が原因で大きな損害を受けた事例があります。
以下に、代表的な例を挙げます。
ドコモ口座不正送金事件(2020年)
NTTドコモが提供する「ドコモ口座」において、銀行口座とドコモ口座を連携する際の本人確認が不十分だったことが原因で、不正送金が行われました。
被害額は約3000万円に上りましたが、この事件をきっかけにセキュリティ体制の甘さが指摘され、ドコモのブランドイメージにも大きな影響を与えました。
さらに事件後の対応や信頼回復に多大なコストを費やすこととなりました。
Yahoo! JAPANへの攻撃(2013年)
Yahoo! JAPANのサーバーが不正アクセスを受け、約2200万人のユーザーIDが流出する可能性がある事案が発生しました。
この事件では、パスワード等認証情報の流出はなかったものの、ユーザーへの影響や信頼低下を防ぐための対応が求められました。
これらの事例からわかるのは、セキュリティの不備による被害が直接的な損失だけでなく、ブランド価値の低下や顧客離れといった長期的かつサービスの存続にかかわる影響を引き起こすということです。
セキュリティ対策を怠った場合のリスクの大きさを意識することが重要です。
リスクとコスト
セキュリティ対策を「コストがかかる」と捉えるのではなく、「将来のリスクを抑えるための投資」と考えてみてください。
実際にどれくらいの費用がかかるのか、具体的に見てみましょう。
たとえば、以下のようなセキュリティ対策には、このくらいの費用がかかります:
- 脆弱性診断:1回50万円~300万円(規模によって上限は変動)
- 脅威モデリングの作成:30万円~200万円
- セキュリティトレーニング:1人あたり10万円程度
金額だけを見ると「高い」と感じるかもしれませんが、これらを怠った場合に受ける損害額では金額の単位が「億」になることも珍しくありません。
セキュリティ対策が万全であるサービスは顧客からの信頼も得やすく、長期的にいいサービスへと成長しやすくなります。
セキュリティ対策にかかる費用はコストではありません、投資です。
2. 開発者とプロダクトマネージャーが知るべき基本的なセキュリティ対策
安全なコードを書く
セキュリティ対策は安全なコードを書くことから始まります。
どれだけ後から対策をしても、コードそのものに問題があるとリスクは残ったままです。
以下のポイントを押さえて、リスクを減らしましょう。
- 入力値の検証を忘れない
ユーザーからの入力値をそのまま使うのは危険です。
SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などWeb経由の攻撃を防ぐために、入力値をしっかりチェックしましょう。 - 重要情報はコードに書かない
APIキーやパスワードなど、機密情報を直接コードに書くのはNG。
環境変数や専用の管理ツールを使うのがベストです。
こんなミスはしないと思いがちですが、脆弱性診断でも多く発見される項目です。 - ライブラリのアップデートを忘れない
便利なオープンソースライブラリですが、脆弱性があるものも多いです。
使っているライブラリは定期的にアップデートして、安全な状態をキープしましょう。
もちろんこれだけですべてを防げるわけではありませんが、これらの基本を押さえるだけでも、攻撃のリスクを減らすことは可能です。
開発プロセスで取り入れるセキュリティのステップ
セキュリティは「リリース直前に考えればいい」では遅すぎます。
開発プロセスの初期から取り入れることで、漏れのない設計をすることができます。
さらに、修正コストも減らすことが可能です。
- プロジェクトの最初にセキュリティ要件を決める
開発をスタートする前に、セキュリティの目標を設定しておきましょう。
これをやっておけば、後から「ここ、セキュリティ的にどうするの?」という無駄な議論を減らせます。 - セキュリティテストを自動化する
手作業でセキュリティをチェックするのは限界があります。
静的解析ツールや動的解析ツールを組み込んで、コードの問題を自動的にチェックする仕組みを作るのがおすすめです。 - チームでセキュリティトレーニングを受ける
開発者だけでなく、プロダクトマネージャーも基本的なセキュリティ知識は必要不可欠です。
全員でトレーニングを受けると、チーム全体のセキュリティ意識も高まります。
セキュリティを「後付け」ではなく、開発プロセスの一部として取り入れることが重要です。
まずはどのステップを組み込み、サービスを守っていくのかを決定してみてください。
外部セキュリティ専門家の活用
プロダクトをより安全にするためには、自分たちのチームだけでなく、外部のセキュリティ専門家に頼ることも重要です。
専門家に依頼すると、第三者の目線でセキュリティをチェックしてもらえるので、見逃していたリスクが見つかることも多くあるでしょう。
- 脆弱性診断でリスクを発見
専門家による脆弱性診断では、攻撃者の視点で脆弱性の調査を実施します。
リリース前やシステムの大規模な変更後に診断を受けることで、攻撃を未然に防ぐことができます。 - 脅威モデルの作成で攻撃パターンを想定
脅威モデルは、どんなリスクがあり得るかを可視化します。
専門家に頼むと、攻撃経路や具体的な防御策まで含めた実践的な計画を立ててくれます。
プロジェクトメンバーのみで対応しようと非常に大きな負担となってしまうため、専門家に頼むのがよいでしょう。
「外部の専門家に頼むなんてお金がかかりそう…」と思うかもしれませんが、サイバー攻撃を受けた後にかかる損害や信頼回復のコストと比べれば、圧倒的に安く済むケースがほとんどです。
プロジェクトメンバーのみで対応したことで漏れが発生するよりは、第三者の目線をしっかりと取り入れたセキュリティ対策を実施することが望ましいです。
3. プロダクトのライフサイクルを通じたセキュリティ管理
設計段階でのセキュリティ考慮
プロダクトのセキュリティは、リリース直前に考えるものではありません。
設計段階から考慮することで、後からの修正コストやトラブルを大きく減らすことができます。
まず重要なのは、「どんな脅威があり得るのか」をしっかり洗い出すことです。
このプロセスで役立つのが脅威モデリングです。
プロダクトに特有のリスクや攻撃パターンを整理し、それに対する防御策をあらかじめ考えることで、設計そのものにセキュリティを組み込むことができます。
また、設計段階では「最小権限の原則」を守ることも重要です。
システムやユーザーが必要以上の権限を持たないように設計することで、攻撃が成功する可能性を減らすことができます。
セキュリティを考慮した設計をすることで、開発全体がスムーズに進み、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
リリース後の脆弱性管理とアップデート
プロダクトをリリースしたら、それで終わりではありません。
むしろ、リリース後こそセキュリティ管理の本番です。
- 脆弱性の早期発見と修正
リリース後も、システムやコードに新しい脆弱性が見つかることがあります。
これを見逃さないために、定期的な脆弱性スキャンを行い、早めに問題を修正する仕組みを整えましょう。
また、セキュリティに関する情報を常に取得していくことも重要です。 - ソフトウェアアップデートの提供
見つかった脆弱性に対処するためには、ユーザーが簡単にアップデートを適用できる仕組みを提供することが必要です。
アップデートのプロセスが煩雑だと、ユーザーがアップデートを怠り、結果的にリスクを抱え込むことになりかねません。 - インシデント対応の準備
万が一、セキュリティインシデントが発生した場合に備え、対応フローをあらかじめ用意しておくと安心です。
連絡体制や顧客への通知手順を決めておけば、トラブルが起きたときにも迅速かつ適切に対応できます。
プロダクトのセキュリティは、リリース後の運用体制が鍵を握ります。
継続的に改善することで、長期的な信頼を築いていきましょう。
チーム全体で取り組むセキュリティ文化の構築
セキュリティは、特定の担当者だけが頑張るものではありません。
チーム全体で取り組む文化を作ることが、強固なセキュリティ体制を築く秘訣です。
- セキュリティを日常業務に組み込む
開発の各フェーズでセキュリティを意識する習慣をつけると、自然とセキュリティリスクが減ります。
たとえば、コードレビューの際にセキュリティの観点からもチェックするなど、日常的なプロセスに組み込むのがポイントです。 - コミュニケーションを活発にする
セキュリティに関する情報や知識を共有するために、チームで定期的にディスカッションや勉強会を行うのもおすすめです。
「この前のプロジェクトでこんなセキュリティリスクが見つかった」といった事例共有は、全員のスキルアップにつながります。 - セキュリティ意識を持てる環境づくり
「セキュリティは面倒」「開発スピードが落ちる」といったネガティブな印象を減らし、ポジティブに取り組める雰囲気を作りましょう。
小さな成功体験を積み重ねることで、チーム全体の意識が高まります。
セキュリティ文化が根付くと、プロダクト開発がスムーズになり、リスクも減少します。
その結果、ユーザーからの信頼を得ることができます。
まとめ
セキュリティはコストではなく、プロダクトや事業を守るための重要な投資です。
しかし、セキュリティ対策には専門的な知識と経験が求められることも事実です。
弊社(トリプルA)はサイバーセキュリティの専門企業として、以下のようなサービスを展開しております。
- 脆弱性診断
- 脅威モデルの作成支援(コンサルティング内)
- セキュリティトレーニング(コンサルティング内)
「セキュリティ対策を実施していきたいけれど、何から始めたらいいかわからない。」「脆弱性診断を頼みたい」などのご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせは下記リンクよりお願いいたします。
https://it-triplea.com/contact/